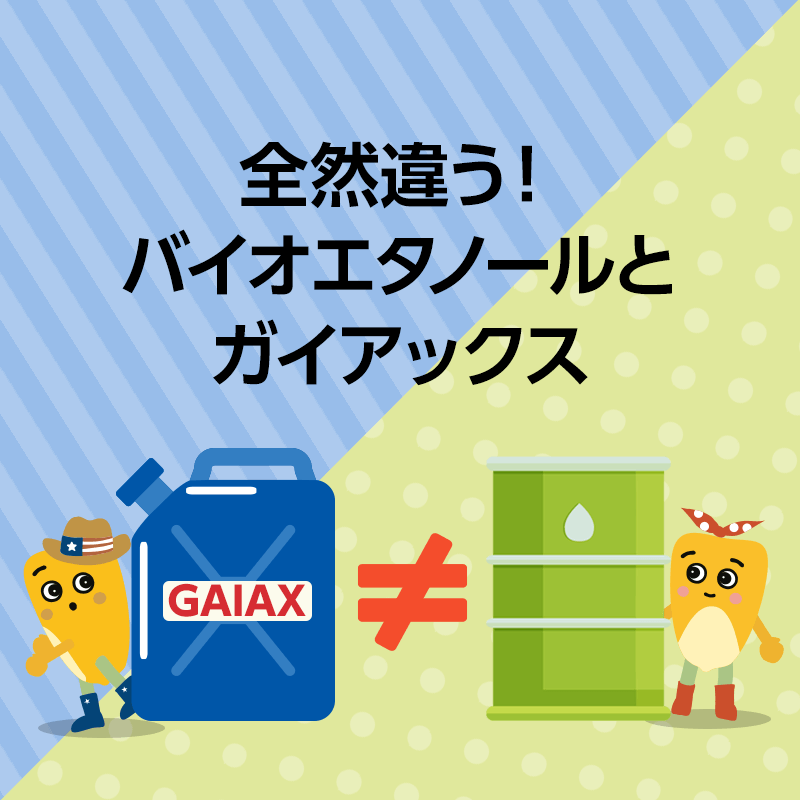\まずは30秒で内容をチェック!/
バイオエタノールとガイアックス:全く異なる2つの燃料
25年ほど前、日本で「ガイアックス」というアルコール系燃料が注目を集めました。ガソリンより安価な代替燃料として一時的に普及しましたが、安全性や環境への影響から市場を去りました。近年、地球温暖化対策として「バイオエタノール」への関心が高まっていますが、一部でガイアックスと混同されることがあります。しかし、この二つは原料も性質も全く異なる燃料です。
今回はバイオエタノールとガイアックスの違いを、原料、CO₂削減効果、車両への影響、法規制などの観点から分かりやすく解説します。
かつて存在した燃料「ガイアックス」とは?
ガイアックス(GAIAX)は、1999年頃から日本のベンチャー企業によって販売されていた高濃度アルコール燃料のブランド名です。

原料と成分:主なガイアックスの原料は100%化石燃料です。韓国などで製造され、ガソリン(炭化水素油)に、石油等を原料とするイソブタノールやイソプロパノールといった合成アルコール、そしてオクタン価向上のための添加剤(MTBE)を混合していました。
特徴と問題点:炭化水素油の割合が当時の揮発油税の対象になる50%を下回っていため、揮発油税の課税対象外となり、レギュラーガソリンよりも安価に販売されていました。しかし、高濃度の合成アルコールなどを混合したため、自動車のアルミ部品を腐食させる問題が指摘され、燃料漏れによる車両火災も発生しました。また、環境省の調査では、排気ガス中の一酸化炭素(CO)や炭化水素(HC)の排出量はガソリンより少ないものの、窒素酸化物(NOx)やアルデヒド類の排出量が多いことが明らかになり、環境負荷も懸念されました。
規制と終焉:税制面での議論や安全性への懸念が高まり、2003年の「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」施行規則の改正により、ガソリンへのアルコール等の混合許容値が厳しく規定されました。これにより、ガイアックスのような高濃度アルコール燃料の販売は実質的に不可能となり、市場から姿を消すこととなりました。

バイオエタノールとガイアックスの主な違い
バイオエタノールとガイアックスは全く異なる燃料です。
主な違いを以下の表にまとめます。
| 比較項目 | バイオエタノール混合ガソリン | ガイアックス |
| ガソリン以外の原料 | トウモロコシ(アメリカ)、サトウキビ(ブラジル)等の植物を原料とするバイオエタノール | 化石燃料(石油等)原料の合成アルコールや添加剤 |
| CO₂削減効果(対ガソリン比) (日本の場合) | ・エタノール単体のCO₂削減効果: ・非LCA:100%=カーボンニュートラル ・LCA:58.46%(米国:トウモロコシ)、67.78%(ブラジル:サトウキビ) (混合した分がCO₂削減効果としてカウントされる) | 化石燃料由来のため、CO₂削減効果は無い |
| 成分(容積比) | E10:ガソリン90%、バイオエタノール10% E85:ガソリン15%、バイオエタノール85%(米・仏等) ほか:E15、E20、E27、E100等 (国により異なる) | ガソリン(炭化水素油)49.3%、その他50.7%(アルコール類33.3%=イソブタノール21.2%+イソプロパノール12.0%+メタノール0.1%、エーテル類17.4%=MTBE(オクタン価向上用添加剤) |
| ガソリンエンジン車両への適合性 | 世界中でE10がスタンダードになっており、E85適合車両も販売されている | 不適合(高濃度アルコールによるアルミ部品の腐食や火災事例あり) |
| 品確法(現行)への適合性 | ~E10:適合(E10対応車) E20:未適合(法改正が必要) | 不適合 |
原料の違い:
- バイオエタノール:トウモロコシ(アメリカなど)、サトウキビ(ブラジルなど)や、あるいは木材チップなど、植物(バイオマス)を原料として作られます。
- ガイアックス:石油などの化石燃料を原料として化学合成されたアルコールを使用していました。
CO₂削減効果の違い:
- バイオエタノール:原料となる植物は、成長過程で光合成により大気中のCO₂を吸収します。そのため、バイオエタノールを燃焼させてCO₂が排出されても、実質的に大気中のCO₂を増加させない「カーボンニュートラル」に近い性質を持っています。ライフサイクル全体で評価(LCA)した場合でも、ガソリンと比較してCO₂排出量を大幅に削減する効果があります。
- ガイアックス:原料が化石燃料であるため、燃焼させるとCO₂が大気中に放出されます。CO₂削減効果は(厳密には化石燃料の種類により異なりますが)基本的にありません。

このように、バイオエタノールは再生可能な植物資源から作られ、CO₂削減に貢献する燃料である一方、ガイアックスは化石燃料由来の合成アルコールを用いた燃料であり、CO₂削減効果は基本的にありません。両者は全く異なるものであることを理解することが重要です。
バイオエタノール混合ガソリンの規格と現状
ガイアックスが市場から姿を消した後、日本ではバイオエタノールの導入が進められてきました。
品確法による規格:ガイアックス問題を受けて2003年に改正された品確法施行規則では、当初ガソリンに混合できるエタノールの濃度は3%まで(E3)と定められました。
E10の扱い:その後、世界的なバイオ燃料導入の流れや技術的検討を経て、特定の基準を満たした自動車(E10対応車)であれば、エタノールを10%まで混合したガソリン(E10)を使用しても問題ないことが確認され、2012年に品確法施行規則が再度改正されました。
利用状況と今後の見通し:現在、E10対応車であれば、E10ガソリンの給油が可能です。自分の車がE10に対応しているかは、給油口の蓋の裏などに記載されたステッカーで確認できます。ただし、現時点(2025年5月)で国内ではE10ガソリンは普及していません。経済産業省は2030年度までにE10の供給開始を目指す方針を2024年11月に示しており、今後の普及が期待されます。

かつて日本で流通したガイアックスと、現在注目されるバイオエタノールは、どちらも「アルコール」を含む燃料ですが、その種類や製造の原料、環境や車両への影響は全く異なります。ガイアックスは化石燃料から作られた合成アルコールを使い、CO₂削減効果はありませんでした。
一方、バイオエタノールは植物由来の再生可能エネルギーであり、カーボンニュートラルに貢献する燃料として期待されています。日本では法整備が進み、E10対応車であればバイオエタノールを10%混合したガソリンを使用できます。エネルギー問題や環境問題を考える上で、これらの違いを正しく理解することが大切です。