「もっと知りたい!バイオエタノール」では、これまでバイオエタノールの基礎知識から国内外の最新動向まで、幅広く情報をお届けしてきました。その中で、SNSやアンケートを通じて読者の皆様から多くのご質問をお寄せいただいています。
そこで、いただいた疑問に専門家がお答えする新企画をスタートします。
記念すべき第一回は、アメリカ穀物バイオプロダクツ協会顧問であり、東京大学名誉教授の横山伸也先生をお迎えし、バイオエタノールに関する様々な疑問にお答えいただきました。
― 本日は、アメリカ穀物バイオプロダクツ協会の顧問であり、バイオマス研究の第一人者で東京大学名誉教授の横山伸也先生にお越しいただきました。これまで「もっと知りたい!バイオエタノール」へ寄せられた質問・疑問にお答えいただくよ!
横山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
― バイオエタノールとは何ですか?どのように使われているのですか?
まず、バイオエタノールについて簡単にお話します。
バイオエタノールは、トウモロコシに含まれるデンプンやサトウキビに含まれる糖分を原料に、発酵させて作るエタノールのことです。主な用途としてはガソリンに混ぜて車の燃料として利用したり、航空機の燃料の原料としても使われます。
そのほか、化粧品、医薬品、消毒用アルコールなど身の回りの製品にも幅広く使われています。
参考として申し上げますと、ビール、日本酒、ウイスキーなどの飲料用のエタノールも燃料用エタノールと、基本的に同じ製法で作られています。燃料用のE10やE20のエタノールは濃度が99.5%以上ですが、飲むお酒のエタノール濃度はビールで4,5%、日本酒やワインは15%程度、ウイスキーは40%程度となっています。
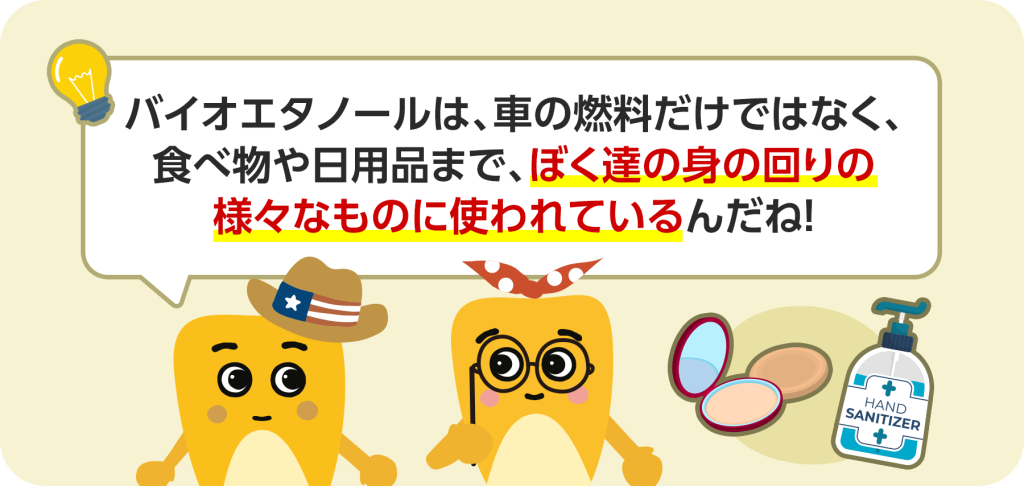
― バイオエタノールはなぜ地球にやさしい燃料だと言われているのですか?
先ほどお話したように、バイオエタノールは、トウモロコシやサトウキビなどのバイオマスから作ります。ここでいうバイオマスとは植物資源のことであり、特にエネルギーや化学原料として活用できるように、ある程度集積した植物資源のことを指します。
バイオマスは、成長するときに光合成で大気中のCO₂を吸収し、みずからの植物体を形成します。そのため、燃料として燃焼しCO₂として大気中に放出しても、吸収したCO₂を大気中に戻すだけなので、大気中のCO₂濃度は変わりません。これをカーボンニュートラルと呼んでいます。石油や石炭のような化石燃料は、燃焼するとCO₂は大気中に蓄積されCO₂濃度が増します。バイオマスから作ったバイオエタノールを燃焼しても、そのようなことは起こりません。このために、地球にやさしい燃料と言われています。
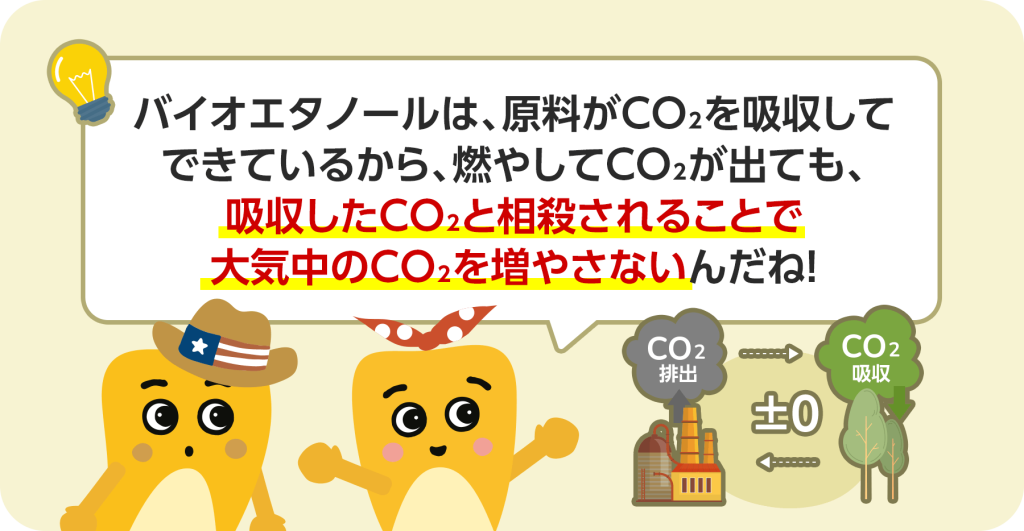
― 日本ではバイオエタノールはどのように利用されているのでしょうか?また、今後利用が拡大していく見込みはありますか?
現在、日本ではガソリンに、バイオエタノールがETBE(エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル)という物質に変換されて入っています。エタノールの量にして82万kLで、混合率は約1.9%です。
ご質問は今後の利用拡大についてですので、2030年度にどの程度、バイオエタノール利用が拡大するかについて推算したものをご紹介したいと思います。
経済産業省は2024年11月に、2030年度にエタノール混合率10%のガソリンであるE10の供給開始、2040年度に混合率20%であるE20の供給開始を目指すという方針を打ち出しました。
(引用:我が国の合成燃料(e-fuel)に関する取組状況及び本協議会の名称変更等を含めた今後の進め方)
経済産業省の資料によると、2024年度のガソリン消費量が4,355万kLであり、先ほど申し上げた通り、エタノールの混合量が82万kLなので1.9%となります。
(引用:2025~2029年度石油製品需要見通し燃料油編)
実はガソリン消費量は、ハイブリッド車や電気自動車の普及、自動車の燃費改善などの理由で年々減少しています。
2040年度にはガソリン需要が4,000万kLになると想定すると、仮にエタノールが直接混合されれば、E10導入により現在の5倍程度の400万kLのバイオエタノールが必要になります。
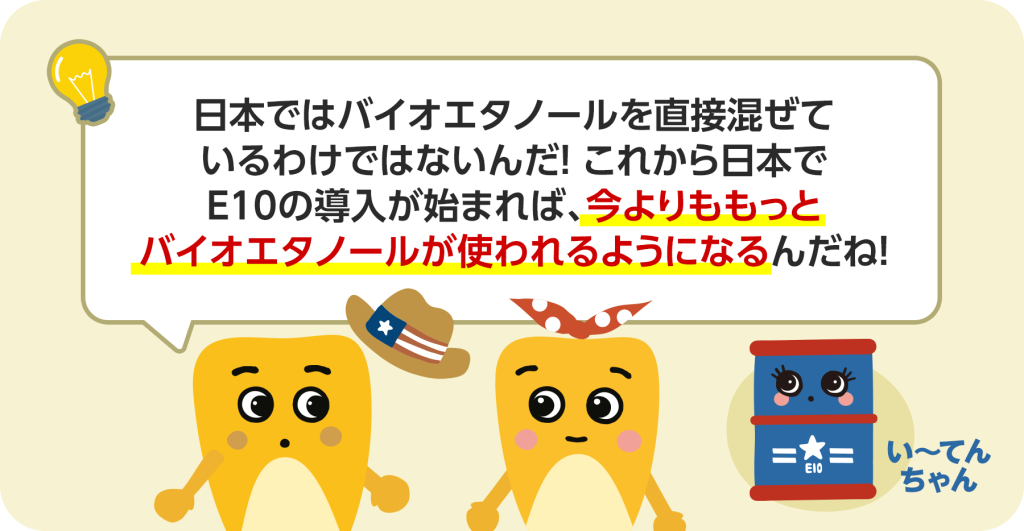
― 世界ではバイオエタノール混合ガソリンは利用されているのでしょうか?
世界ではE10が標準となっています。アメリカはE10、E15、E85が使用でき、カナダはE10,ブラジルはE27、ヨーロッパはE10、フランスはE10とE85です。電気自動車に熱心だったイギリスも、4年前からE10を義務化しています。アジアではインドやタイやフィリピンがE10からE20を目指しています。中国も州にもよりますが、E5とE10が普及している状況です。すべて、ETBEではなくエタノールが直接混合されていますが、特段の問題や支障はありません。
(引用:我が国の合成燃料(e-fuel)に関する取組状況及び本協議会の名称変更等を含めた今後の進め方)
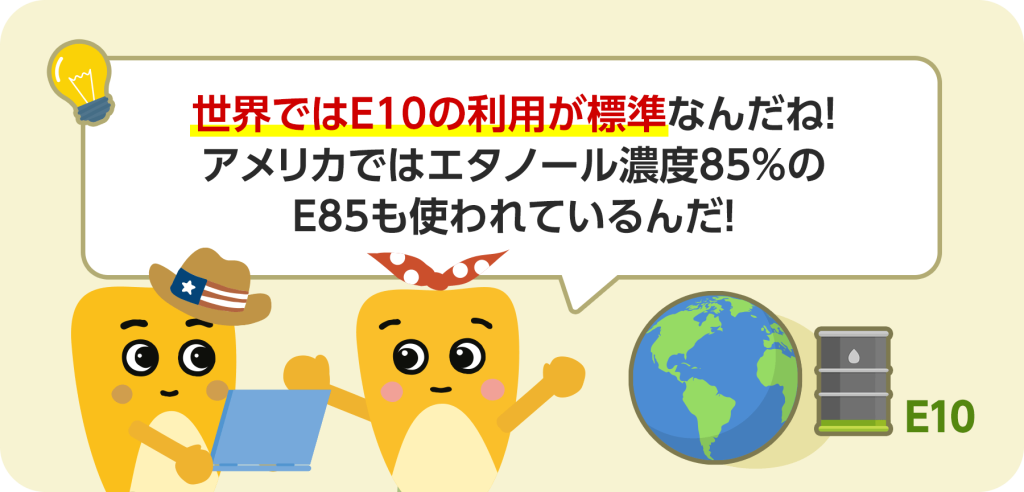
― バイオエタノール混合ガソリンが普及すると私たちの生活にどのようなメリットがありますか?
一点目は、車のエンジンに与える負担を軽減できるということです。車の燃料にはオクタン価という指標があり、この数値が高いほど、ノッキングという爆発現象が、起きにくいと言われています。
高い出力でエンジンを回転させていると、エンジン内において、ガソリンと空気の混合気体に点火プラグで点火させる前に、爆発が起こることがあります。点火前に爆発が起こると、ピストンが想定外の動きをして、エンジンが逆回転するなどして、異常な音や振動が発生します。この現象がノッキングで、エンジンに悪影響を及ぼすことになりますが、オクタン価が高いエタノールを混合することで、この現象を軽減することができます。
レギュラーガソリンのオクタン価は89ですが、エタノールのオクタン価は111です。エタノールを混合することでオクタン価が上がります。エタノール混合ガソリンはアンチノッキング性に優れているので、エンジンへの負担を軽減できます。
二点目がエネルギー安全保障上のメリットです。現在、わが国は原油の90%以上を中東に依存していますが、燃料の10%を米国などから輸入することで、エネルギー供給源の多様化になり、エネルギーの安全保障にも繋がります。
(引用:第2部 第1章 第3節 一次エネルギーの動向 │ 令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023))
三点目は、現在のエタノールに対する免税が続いて、エタノールとガソリンの価格が現状のような推移をすると、E10ガソリンはレギュラーガソリンより安くなります。
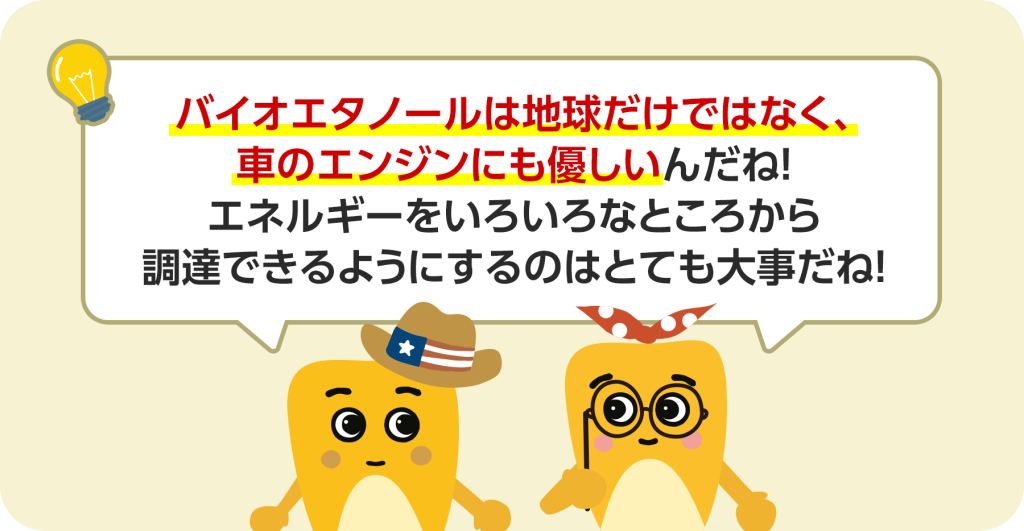
実は身近なところで生活を支えているバイオエタノール。世界ではE10以上の燃料が日常的に使われているということでした。しかし、トウモロコシやサトウキビを原料にする、ということは食料不足に繋がったりしないのでしょうか?
次回は食べ物とバイオエタノールとの関係を横山先生へ質問します。
▼中編はこちら
(中編)東大名誉教授 横山先生に疑問・質問を聞いてみた


