前編では、バイオエタノールが実は私たちの身近なところで生活を支えていること、世界ではE10以上のバイオエタノール混合ガソリンが日常的に使われていること、バイオエタノールが普及することによるメリットなどを教えていただきました。
今回はバイオエタノールと食べ物との関係について、引き続き、横山先生にお答えいただきます。
― トウモロコシからバイオエタノールを作ると、食料不足に繋がるのではないでしょうか?
バイオエタノールの原料となるトウモロコシは、デントコーンと呼ばれ、元々家畜の飼料用です。人間が食べるトウモロコシはスイートコーンと呼ばれ、全く別物です。2022年のアメリカでのデントコーンの生産量は、3億5,800万トンで、スイートコーンは290万トンです。食料用のスイートコーンは0.8%にすぎません。粗々ですが、デントコーンの3分の1が家畜飼料、3分の1がエタノール用、3分の1が輸出や産業用に使われています。
(引用:USDA PSD)
わが国の場合ですと、毎年デントコーンを、1,500万トンから1,600万トンを輸入していますが、スイートコーンの生産量は25万トン程度で、2%以下にすぎません。食料とは関係が薄いことがわかります。
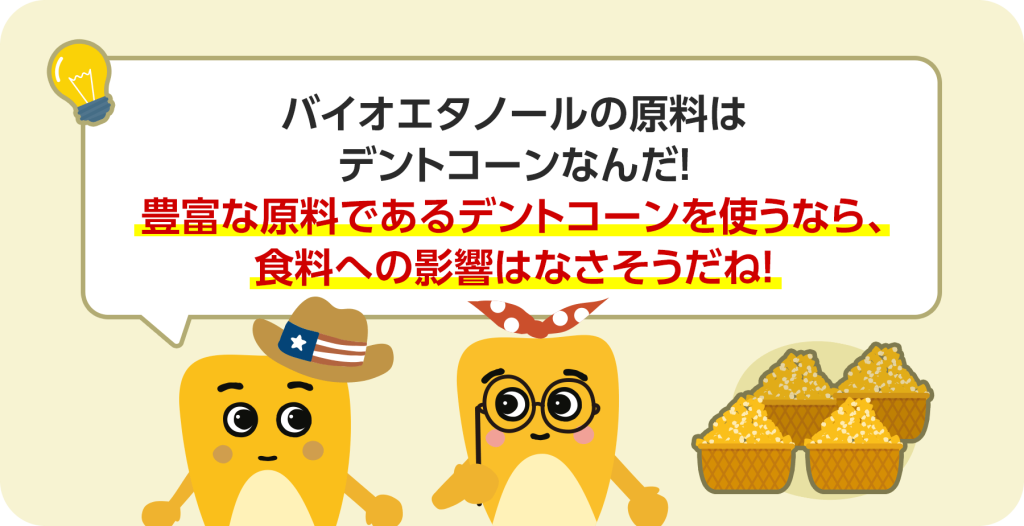
― バイオエタノールの生産量が上がることでトウモロコシなどの穀物価格やお肉などの食料価格は上がるのではないでしょうか?
エタノールを増産しても、他の作物の耕作地を使ってトウモロコシを生産しているわけではないので、穀物価格への影響は少ないと思います。アメリカでは過去60年間、トウモロコシの栽培面積を増やすことなしに、単位面積当たりの収量が3倍に増加しています。
家畜飼料も十分に需要を満たしており、トウモロコシが原因で穀物価格が高騰するといった状況は確認されていません。
(引用:USDA PSD)
世界的にはタンパク質の不足が指摘されています。エタノール生産に伴って作られるDDGSと呼ばれる、高タンパクの家畜飼料は、肉牛や豚肉などを作る畜産業にも貢献しています。
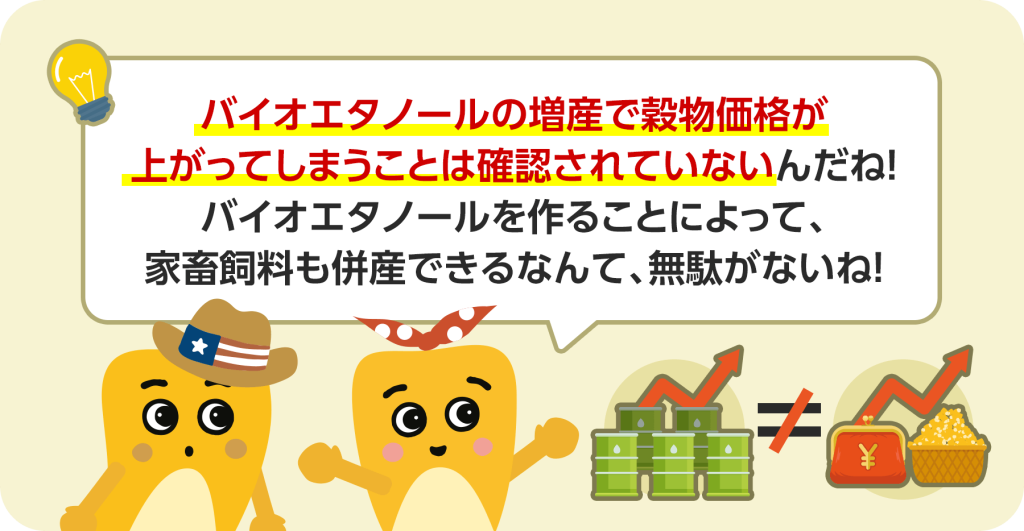
― バイオエタノール原料の確保のため、森林伐採など土地への影響が気になります。問題ないのでしょうか?
今、申し上げた通り、アメリカでは過去60年間、耕作地を増やさずに収量を上げてきました。森林伐採による耕作地の拡大などで、収穫量を上げてきたわけではありません。
品種改良、農業機械の大型化や自動化、農業技術の発展により生産性を上げてきました。
現在、トウモロコシの平均収量は1エーカー当たり185ブッシェルで、これは1ヘクタール当たり約11トンに相当します。この収穫量は年々増加して、年平均2%で伸びています。従って、環境に負荷を与えることなく増産が続くと見込まれます。
(引用:USDA PSD)

― バイオエタノールは製造コストが高いと聞きました。普及にあたりコスト面・技術面での課題はありますか?
国産バイオエタノールのことと思います。原料としてアメリカからの輸入トウモロコシを利用する可能性や、コメを利用する可能性があります。いずれにしても、アメリカのような大規模な経営は無理なので、労力やコストをかけない方法が大事です。
わが国では、耕作放棄地が約42万ヘクタールあるとされています。机上の計算ではありますが、ここに多収米あるいはトウモロコシを植えれば、少なくとも150万kLのエタノールが生産できることになります。この何分の1でも生産できればそれなりの意味があると思います。
国産エタノールは量的にも限界があるとは思いますが、できる範囲で国産化し、その量を増やしていくことは意義があると思います。例えば、耕作放棄地を利用することは、エタノール生産のためだけではなく、耕作地の保全という効果もあり食料安全保障にも貢献します。

― てんぷら油などの廃食油やゴミからもバイオ燃料を作れるとテレビで見ました。あえて食にも関連するトウモロコシを使い、バイオエタノールを生産する必要はあるのでしょうか?
航空機用の燃料としてSAFの導入が、国際的な規約で定められています。SAFは持続可能な航空燃料という意味です。現在、SAF製造にはいくつかの方法がありますが、有力な二つの方法があります。
一つはテレビなどでも時折紹介される、てんぷら油などの廃食用油を原料とするHEFAと呼ばれる方法です。廃色用油を水素化処理して作る方法です。原料が廃棄物なのでコストは安いのですが、原料に限りがあります。
次に期待されているのがエタノールを原料とするATJ、つまりアルコール to ジェットと、呼ばれる方法です。エタノールを脱水して作るエチレンを重合して作ります。前にも話した通り、アメリカのトウモロコシ生産は耕作地を増やさず増産しているので、食料競合には当てはまりません。
SAF需要が一番多いアメリカは、“SAF Grand Challenge”として、2030年に30億ガロンのSAF製造を目指しています。これは約1,100万kLに相当します。一方、アメリカのエタノールの生産余力は、940万kLと言われています。SAFは廃食用油の他に、大豆や菜種からも作られるので、食料生産に影響を与えることは少ないと考えられます。
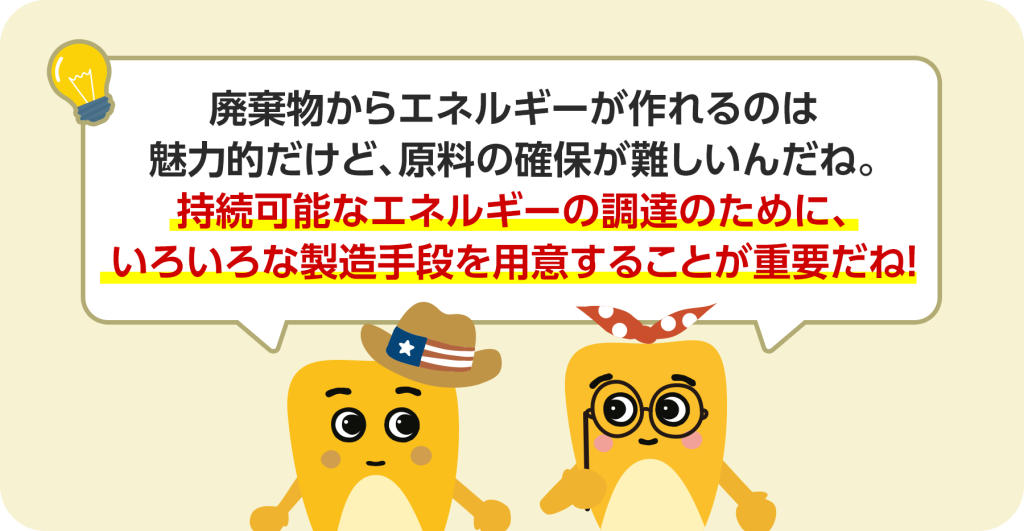
バイオエタノールは耕作地を増やさず収穫量を上げる、強固なトウモロコシ生産によって支えられており、食料不足や穀物価格高騰への影響が薄いことがわかりました。また、バイオエタノール生産に伴って作られるDDGSという高タンパクな家畜飼料により、間接的に食料生産へも貢献しています。
そんなバイオエタノールですが、日本へもいよいよE10導入が近づいています。読者の方からは、本当にクルマに給油して問題ないのか?ガソリン価格は安くなるのか?などたくさんの質問をいただいています。
後編では私たちの生活への具体的な影響について、横山先生へお答えいただきます。
▼後編はこちら
(後編)東大名誉教授 横山先生に疑問・質問を聞いてみた


